基本技3(正面打ち一教・表)
岡です)
正面打ち一教の表は、受けが正面打ちを振りかぶった瞬間に入身し、手刀を呼吸法で下から切り上げるようにして手首、肘を制します。そして前方に切り下しながら前進する力でうつ伏せに抑えます。手刀の切り上げから切り下しまで、腕の力だけに頼らず、入身の前進する力を生かすことが大切です。
ここでは正面打ち一教・表の方法とポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道、技を極める合気道)
正面打ち一教(表)
1、右相半身で構えから、受けが正面打ちを振りかぶる。
2、それに合わせて取りは前方に入身し、正面打ちを右手刀で制しながら下から左手で肘をつかむ。
入身の体さばきに合わせて左手で肘、右手で手首を制する。
正面打ちを制する時は、いきなり手首をつかまず、手刀を合わせてから呼吸力を活かし、下から切り上げる。
肘は自分の正面でつかみ、肘を返すイメージで切り下す。
3、前進しつつ肘と手首を切り下し、受けを崩す。
4、さらに前進し、受けをうつ伏せにし、肩、肘、手首を畳につけて抑える。
受けの肩が浮かないように、脇を直角に開いて抑える。
腕を伸ばすような感じ。
内側の膝は受けの脇腹、外側の膝は手首の下にしっかりつける。
腕の力ではなく、自分の体重を生かし跪座で抑える。
正面打ち一教の表は、受けが正面打ちを振りかぶった瞬間に入身し、手刀を呼吸法で下から切り上げるようにして手首、肘を制します。そして前方に切り下しながら前進する力でうつ伏せに抑えます。手刀の切り上げから切り下しまで、腕の力だけに頼らず、入身の前進する力を生かすことが大切です。
ここでは正面打ち一教・表の方法とポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道、技を極める合気道)
正面打ち一教(表)
1、右相半身で構えから、受けが正面打ちを振りかぶる。
2、それに合わせて取りは前方に入身し、正面打ちを右手刀で制しながら下から左手で肘をつかむ。
入身の体さばきに合わせて左手で肘、右手で手首を制する。
正面打ちを制する時は、いきなり手首をつかまず、手刀を合わせてから呼吸力を活かし、下から切り上げる。
肘は自分の正面でつかみ、肘を返すイメージで切り下す。
3、前進しつつ肘と手首を切り下し、受けを崩す。
4、さらに前進し、受けをうつ伏せにし、肩、肘、手首を畳につけて抑える。
受けの肩が浮かないように、脇を直角に開いて抑える。
腕を伸ばすような感じ。
内側の膝は受けの脇腹、外側の膝は手首の下にしっかりつける。
腕の力ではなく、自分の体重を生かし跪座で抑える。
基本技2(相半身片手取り一教・裏)
岡です)
相半身片手取り一教の裏技は、受けの側面に入身した後、転換して体を回転させながら、相手を円運動に導き倒す技です。第一教の抑えでのポイントは、受けの肩を畳につけ、肘が曲がらないように伸ばしながら手のひらを上に向けることです。
ここでは、相半身片手取り一教(裏)の方法とポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
相半身片手取り一教(裏)
1、右相半身の構えから、受けが取りの右手首を右手でつかむ。
2、右手首をつかませると同時に右手刀を切り上げ、受けの側面に入身し、上がった肘を左手で下からつかむ。
3、肘を制しつつ、踏み込んだ左足を軸に素早く転換する。
4、転換の体さばきと同時に、受けの肘と手首を切り下す。
5、手首と肘を制しながら受けをうつ伏せにし、表技同様に抑える。
受けの肘が浮かないようにする。
手のひらを上に向ける。
相半身片手取り一教の裏技は、受けの側面に入身した後、転換して体を回転させながら、相手を円運動に導き倒す技です。第一教の抑えでのポイントは、受けの肩を畳につけ、肘が曲がらないように伸ばしながら手のひらを上に向けることです。
ここでは、相半身片手取り一教(裏)の方法とポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
相半身片手取り一教(裏)
1、右相半身の構えから、受けが取りの右手首を右手でつかむ。
2、右手首をつかませると同時に右手刀を切り上げ、受けの側面に入身し、上がった肘を左手で下からつかむ。
3、肘を制しつつ、踏み込んだ左足を軸に素早く転換する。
4、転換の体さばきと同時に、受けの肘と手首を切り下す。
5、手首と肘を制しながら受けをうつ伏せにし、表技同様に抑える。
受けの肘が浮かないようにする。
手のひらを上に向ける。
基本技1(相半身片手取り一教・表)
岡です)
合気道の技は、相手の攻撃方法や構えかたで無限に広がりますが、その基本になる技はそう多くはありません。第一教~四教、入り身投げ、四方投げ、天地投げ、小手返しがそれにあたると思います。今回から合気道の基本技をピックアップし紹介していきたいと思います。
今回は「相半身片手取り一教(表)」です。
一教とは、受けの攻撃線をはずしながらひじ関節と手首をつかみうつ伏せに押さえる固め技です。相半身片手取り一教(表)は、受けの側面に入身しながら前進する力を活かして手刀を切り上げ切り下ろします。では相半身片手取り一教(表)の方法とポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
相半身片手取り一教(表)
1、右相半身に構える。
2、受けが取りの右手首をつかむ。
3、つかませた右手を手刀状にし、弧を描くように手刀切り上げ、受けの脇を開かせ右ひじを浮かせる。
手刀の切り上げで重要なのは、弧を描く軌道にのせる事。
受けの肘を十分に上げて脇を開かせる事で姿勢を崩しやすくなる。
4、歩み足で受けの側面に入身しながら左手で右の肘を制し、手刀を切り下す。
右手刀の切り上げによって上がった受けの肘をつかんで制したら、前進する力と手刀の切り下ろしの動作を合わせ、受けを崩す。ここで正確に手首と肘を制することで一教の固め技つながる。
手刀を切り下すときは、大きく弧を描くイメージで行う。
入身の体さばきによる前進力を手刀にのせる。
5、手首と肘を制しつつさらに前進し受けをうつ伏せに崩す。
6、腕を制しながら受けをうつ伏せにし、左ひざをつく。
7、受けの肩、肘、手首を畳に付け、重心をおろし抑え制する。
両手と両ひざの4点で抑える。
受けの腕が真っ直ぐになるよう伸ばし、両手で手首と肘を制しながら、両ひざを受けの脇と手首に密着させて力を逃がさないようにする。抑える時の足は跪座にする。
合気道の技は、相手の攻撃方法や構えかたで無限に広がりますが、その基本になる技はそう多くはありません。第一教~四教、入り身投げ、四方投げ、天地投げ、小手返しがそれにあたると思います。今回から合気道の基本技をピックアップし紹介していきたいと思います。
今回は「相半身片手取り一教(表)」です。
一教とは、受けの攻撃線をはずしながらひじ関節と手首をつかみうつ伏せに押さえる固め技です。相半身片手取り一教(表)は、受けの側面に入身しながら前進する力を活かして手刀を切り上げ切り下ろします。では相半身片手取り一教(表)の方法とポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
相半身片手取り一教(表)
1、右相半身に構える。
2、受けが取りの右手首をつかむ。
3、つかませた右手を手刀状にし、弧を描くように手刀切り上げ、受けの脇を開かせ右ひじを浮かせる。
手刀の切り上げで重要なのは、弧を描く軌道にのせる事。
受けの肘を十分に上げて脇を開かせる事で姿勢を崩しやすくなる。
4、歩み足で受けの側面に入身しながら左手で右の肘を制し、手刀を切り下す。
右手刀の切り上げによって上がった受けの肘をつかんで制したら、前進する力と手刀の切り下ろしの動作を合わせ、受けを崩す。ここで正確に手首と肘を制することで一教の固め技つながる。
手刀を切り下すときは、大きく弧を描くイメージで行う。
入身の体さばきによる前進力を手刀にのせる。
5、手首と肘を制しつつさらに前進し受けをうつ伏せに崩す。
6、腕を制しながら受けをうつ伏せにし、左ひざをつく。
7、受けの肩、肘、手首を畳に付け、重心をおろし抑え制する。
両手と両ひざの4点で抑える。
受けの腕が真っ直ぐになるよう伸ばし、両手で手首と肘を制しながら、両ひざを受けの脇と手首に密着させて力を逃がさないようにする。抑える時の足は跪座にする。
呼吸法3(座技呼吸法)
岡です)
取りと受けが正座で相対し、両手をつかませて行う呼吸力の養成法を「座技呼吸法」といいます。
ここでは座技呼吸法の方法とポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
座技呼吸法)
1、正座で相対し、受けに両手首を外側からつかませる。
2、両手刀を受けの腕の内側で切り上げる。
3、両手刀を十分に切り上げ、受けの両脇を浮かせる。
4、受けの両脇が上がったら、受けの側面に片足を踏み込み、両手刀を切り下ろし、受けの体勢を崩す。
5、両手刀で受けの体を制し、抑える。抑える際は前傾になり過ぎないように注意する。
ポイント!
手刀を切り上げる際は、まっすぐに突き上げず、肩肘をやわらかく使い、手首を回転させるようにする。腰を中心にお腹から力を出すイメージで行うことで、呼吸力が活かされる。
取りと受けが正座で相対し、両手をつかませて行う呼吸力の養成法を「座技呼吸法」といいます。
ここでは座技呼吸法の方法とポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
座技呼吸法)
1、正座で相対し、受けに両手首を外側からつかませる。
2、両手刀を受けの腕の内側で切り上げる。
3、両手刀を十分に切り上げ、受けの両脇を浮かせる。
4、受けの両脇が上がったら、受けの側面に片足を踏み込み、両手刀を切り下ろし、受けの体勢を崩す。
5、両手刀で受けの体を制し、抑える。抑える際は前傾になり過ぎないように注意する。
ポイント!
手刀を切り上げる際は、まっすぐに突き上げず、肩肘をやわらかく使い、手首を回転させるようにする。腰を中心にお腹から力を出すイメージで行うことで、呼吸力が活かされる。
呼吸法2(諸手取り呼吸法・裏)
岡です)
「諸手取り呼吸法 裏」は、入身の後に転換し、受けの側面で手刀を切り上げます。入身転換の体さばきと手刀の動きをあわせることが重要です。
ここでは諸手取り呼吸法 裏の方法とポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
諸手取り呼吸法(裏)
1、受けに左手首を諸手でつかませます。
2、手首をつかませるのと同時に、受けの前足の外側に左足を進め入身します。
3、つかませた左手を手刀状にしつつ、踏み出した足を軸に右足を引き転換します。
4、転換の足さばきに合わせて左手刀を自分の中心で弧を描くように切り上げます。
5、転換後、右足に重心を移しながら、左足を大きく後方へ踏み込みます。
6、両手刀を切り下ろし、投げて残身をとります。
ポイント!
表技同様に、腕の力に頼るのではなく、正しい体さばきから生まれる足腰の力を活かす。
入身と転換の足さばきと手刀の切り上げを一連の流れで行うことで、呼吸力が十分発揮される。
「諸手取り呼吸法 裏」は、入身の後に転換し、受けの側面で手刀を切り上げます。入身転換の体さばきと手刀の動きをあわせることが重要です。
ここでは諸手取り呼吸法 裏の方法とポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
諸手取り呼吸法(裏)
1、受けに左手首を諸手でつかませます。
2、手首をつかませるのと同時に、受けの前足の外側に左足を進め入身します。
3、つかませた左手を手刀状にしつつ、踏み出した足を軸に右足を引き転換します。
4、転換の足さばきに合わせて左手刀を自分の中心で弧を描くように切り上げます。
5、転換後、右足に重心を移しながら、左足を大きく後方へ踏み込みます。
6、両手刀を切り下ろし、投げて残身をとります。
ポイント!
表技同様に、腕の力に頼るのではなく、正しい体さばきから生まれる足腰の力を活かす。
入身と転換の足さばきと手刀の切り上げを一連の流れで行うことで、呼吸力が十分発揮される。
呼吸法1(諸手取り呼吸法・表)
岡です)
呼吸法は呼吸力(全身の力を効率よく発揮させる力)を養う稽古法です。稽古の中では「諸手取り呼吸法・表裏」と「座技呼吸法」がよく用いられます。
諸手取り呼吸法(表)は、受けに手首をつかませたら、入身をすると同時に呼吸力を充実させ手刀を切り上げ、切り下ろします。
ここでは諸手取り呼吸法(表)の方法とポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
諸手取り呼吸法(表)
1、受けに左手首を諸手でつかませます。
2、左手首をつかませるのと同時に、左足を軸に右足を受けの前足の側面に踏み出し、入身します。
3、入身の足さばきに合わせて呼吸力を充実させた左手刀を自分の中心で切り上げます。
4、左足を踏み込み、左足に重心を移しながら弧を描くように左手刀切り下ろします。
5、足腰の力を手刀に乗せながら切り下ろし、受けを崩します。
6、最後まで姿勢を崩さないように注意します。
ポイント!
手首をつかませてから切り上げ切り下ろしまでの一連の動作の間、手刀が自分の中心に来るようにする。こうすることで、腕の力だけでなく体全体の力が使いやすくなり、呼吸力が活かされる。
呼吸法は呼吸力(全身の力を効率よく発揮させる力)を養う稽古法です。稽古の中では「諸手取り呼吸法・表裏」と「座技呼吸法」がよく用いられます。
諸手取り呼吸法(表)は、受けに手首をつかませたら、入身をすると同時に呼吸力を充実させ手刀を切り上げ、切り下ろします。
ここでは諸手取り呼吸法(表)の方法とポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
諸手取り呼吸法(表)
1、受けに左手首を諸手でつかませます。
2、左手首をつかませるのと同時に、左足を軸に右足を受けの前足の側面に踏み出し、入身します。
3、入身の足さばきに合わせて呼吸力を充実させた左手刀を自分の中心で切り上げます。
4、左足を踏み込み、左足に重心を移しながら弧を描くように左手刀切り下ろします。
5、足腰の力を手刀に乗せながら切り下ろし、受けを崩します。
6、最後まで姿勢を崩さないように注意します。
ポイント!
手首をつかませてから切り上げ切り下ろしまでの一連の動作の間、手刀が自分の中心に来るようにする。こうすることで、腕の力だけでなく体全体の力が使いやすくなり、呼吸力が活かされる。
体さばき3(転身)
岡です)
受けの攻撃を回転してかわし、相手の側面に入る体さばきが転換ですが、体を横に開いてから回転し攻撃をかわすのが「転身」です。
受けが攻撃を仕掛けてきたのと同時に後ろ足を開き、その足を軸に前足を回転させます。攻撃の勢いを利用して受けを崩すよう心がけましょう。
ここでは転身の方法とそのポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
転身)
横面打ちに対する転身
1、左相半身に構える。
2、受けが右手刀で横面打ちをしてくるのと同時に、取りは両手刀で横面打ちを制し、右足を横に開く。
3、右足を軸に左足を引きつつ、体を回転させる。
4、回転の動作と同時に受けの右手刀を手刀で切りおろし、受けの姿勢を崩す。
肩取りでの転身
1、取りは左肩を取らせるのと同時に、後ろ足を横に開きながら右手で当身を入れる。
2、横に踏み出した足を軸に前足を引きつつ、体を回転させる。
3、体の回転と同時に、当身を入れた手刀で受けの腕を切り下ろし、崩す。
ポイント!
転身でポイントとなるのが、前足の動き。上記の場合、右足を斜めに開くように踏み出し、その足を軸に左足を回転させることで、攻撃をかわし、受けの体勢を崩す。この足さばきに合わせて手形なの切り上げ、切り下ろしを行うこと。
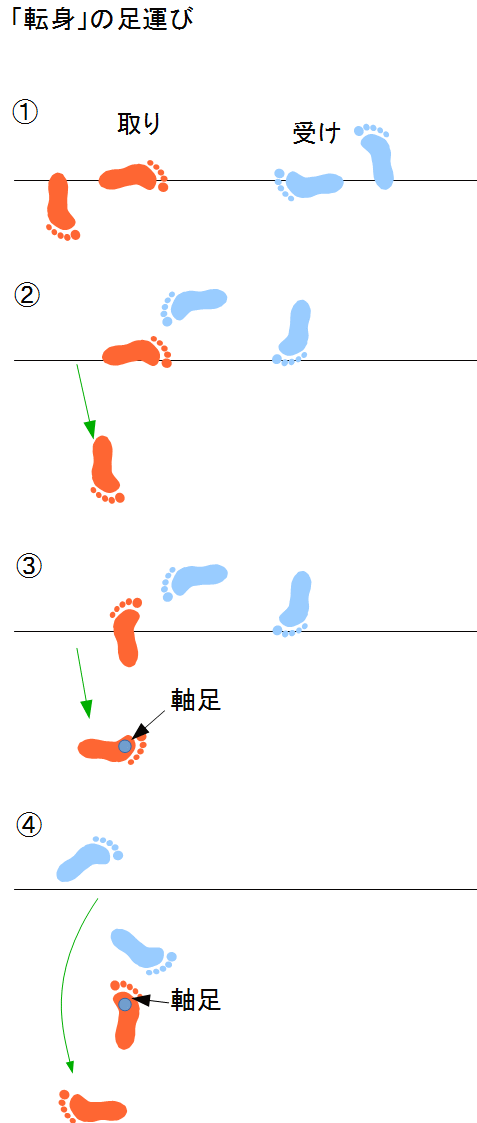
受けの攻撃を回転してかわし、相手の側面に入る体さばきが転換ですが、体を横に開いてから回転し攻撃をかわすのが「転身」です。
受けが攻撃を仕掛けてきたのと同時に後ろ足を開き、その足を軸に前足を回転させます。攻撃の勢いを利用して受けを崩すよう心がけましょう。
ここでは転身の方法とそのポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
転身)
横面打ちに対する転身
1、左相半身に構える。
2、受けが右手刀で横面打ちをしてくるのと同時に、取りは両手刀で横面打ちを制し、右足を横に開く。
3、右足を軸に左足を引きつつ、体を回転させる。
4、回転の動作と同時に受けの右手刀を手刀で切りおろし、受けの姿勢を崩す。
肩取りでの転身
1、取りは左肩を取らせるのと同時に、後ろ足を横に開きながら右手で当身を入れる。
2、横に踏み出した足を軸に前足を引きつつ、体を回転させる。
3、体の回転と同時に、当身を入れた手刀で受けの腕を切り下ろし、崩す。
ポイント!
転身でポイントとなるのが、前足の動き。上記の場合、右足を斜めに開くように踏み出し、その足を軸に左足を回転させることで、攻撃をかわし、受けの体勢を崩す。この足さばきに合わせて手形なの切り上げ、切り下ろしを行うこと。
体さばき2(転換)
岡です)
「転換」は、半身の構えから前足を一歩踏み出し、その足を軸に体を回転させる動きです。回転させる際は、受けの攻撃の勢いを利用し、自分の円運動の中に導きいれるようにさばきます。転換は入身と組み合わせて用いられる事が多いので、入身と一緒に覚えるとようにしましょう。
ここでは、転換の方法とそのポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
転換)
1、右逆半身の構えから、受けが前進しつつ取りの右手首をつかむ。
2、手首をとらせるのと同時に、右足を受けの前足の外側面に踏み出し、攻撃線をはずすよう入身する。
3、前に出した右足を軸に180度体を回転させる。
4、左足を後方に引きながら、体全体を受けの側面に移し、半身になる。同時に両手刀を前方に出す。
ポイント!
体を回転させた後も、半身になれるよう正しく足の位置をそろえる。
転換を行う際に、体を回転させることにばかり意識がいき、軸がぶれてしまうことがある。常に安定した姿勢を保つために、足で回るのではなく腰で回るようにイメージするとよい。自分の中心軸を意識し、上体を傾けないよう注意して回転し、転換後も中心軸の意識を保つようにする。
「転換」は、半身の構えから前足を一歩踏み出し、その足を軸に体を回転させる動きです。回転させる際は、受けの攻撃の勢いを利用し、自分の円運動の中に導きいれるようにさばきます。転換は入身と組み合わせて用いられる事が多いので、入身と一緒に覚えるとようにしましょう。
ここでは、転換の方法とそのポイントを紹介します。
(参考資料 もっとうまくなる合気道)
転換)
1、右逆半身の構えから、受けが前進しつつ取りの右手首をつかむ。
2、手首をとらせるのと同時に、右足を受けの前足の外側面に踏み出し、攻撃線をはずすよう入身する。
3、前に出した右足を軸に180度体を回転させる。
4、左足を後方に引きながら、体全体を受けの側面に移し、半身になる。同時に両手刀を前方に出す。
ポイント!
体を回転させた後も、半身になれるよう正しく足の位置をそろえる。
転換を行う際に、体を回転させることにばかり意識がいき、軸がぶれてしまうことがある。常に安定した姿勢を保つために、足で回るのではなく腰で回るようにイメージするとよい。自分の中心軸を意識し、上体を傾けないよう注意して回転し、転換後も中心軸の意識を保つようにする。
記事カテゴリー
ブログ内検索
記事投稿について
道場生のみなさんへ
ID,パスワードをご存知の方は、下のリンクの「新しい記事を書く」か「管理画面」よりログインし記事掲載下さい。
ご存じない方や方法がわからない方は、ブログ上部の「問合せメール」から氏名、記事内容を書いて送信下されば後日管理者が掲載します。
ご存じない方や方法がわからない方は、ブログ上部の「問合せメール」から氏名、記事内容を書いて送信下されば後日管理者が掲載します。
内容は日記レベルで十分です。気軽に投稿ください。
最新のコメント
アーカイブ
ブログ管理担当
忍者広告
PR


